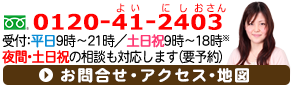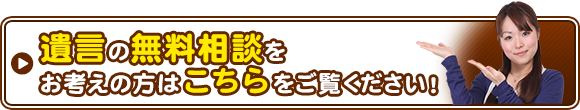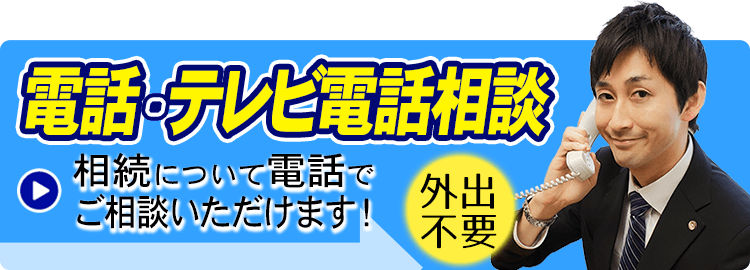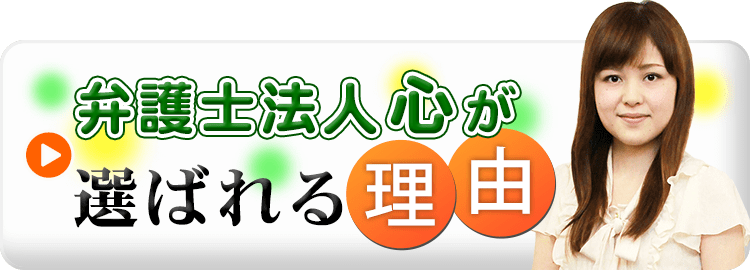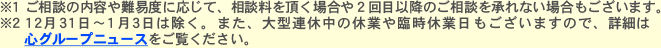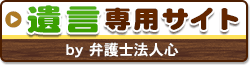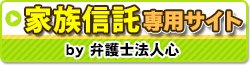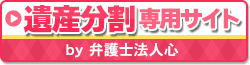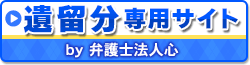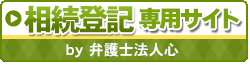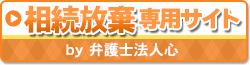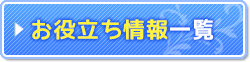遺言の検認手続きの流れと必要書類
1 遺言の検認手続きの概要
お亡くなりになられた方が遺された遺言が自筆証書遺言で、かつ法務局による保管制度を利用していなかった場合には、家庭裁判所で遺言の検認手続きを行う必要があります。
多くの相続手続きにおいて、検認手続きを済ませていない遺言は利用できないためです。
遺言の検認をするためには、戸籍謄本類を収集したうえで、検認の申立書と一緒に管轄の家庭裁判所へ申立てをします。
そして、検認の期日(家庭裁判所で検認をする日)に、遺言の原本を持参し、検認手続きを終えたら検認済証明書を取得します。
以下、検認手続きの流れについて詳しく説明します。
2 検認申立てに必要な書類
検認申立てをする際には、次の書類が必要です。
①検認申立書
②自筆証書遺言(封がしてある場合には、開封してはいけません)
③被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本
※戸籍謄本類については、③、④は最低限必要なものとなります。相続人が直系尊属の場合や、配偶者のみの場合、兄弟姉妹の場合、代襲相続人がいる場合などには、追加で必要となるものもあります。
⑤800円分の収入印紙、予納郵券
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
3 検認の申立て~検認手続き
検認の申立てをする際には、管轄の家庭裁判所に必要書類を提出(郵送も可能)します。
管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域
検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人に対して、検認を行う日時についての通知書面が送付されます。
検認には、最低限申立人は出席する必要はありますが、それ以外の相続人は必ずしも出席する必要はありません。
検認の日には、裁判所へ遺言書の原本を提出し、検認が行われます。
これにより、検認の日時において、提出された遺言書が存在していたことが確認されます。
検認が終了したら、検認が行われたことを第三者に示せるようにするため、家庭裁判所で検認済証明書を申請して取得します。
以降の相続に関する手続きにおいては、多くの場合、遺言書と検認済証明書をセットで使用します。
信託銀行と専門家の違い 遺産相続に強い弁護士の選び方と相談・依頼するメリット